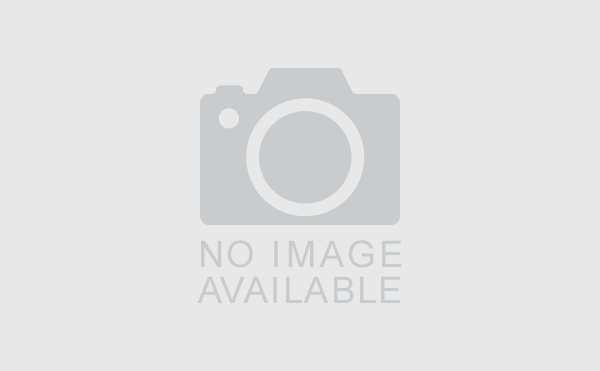犬の歯周病は抜歯が必要?抜歯が検討される症状・手術の方法・予防までわかりやすく解説
犬の歯周病は、進行すると強い口臭や痛みを引き起こし、最終的に全身麻酔による抜歯が必要になることもあります。
抜歯と聞くと不安になる飼い主様も多いことでしょう。
しかし、手術が終わると痛みや感染から解放され、食欲や元気を取り戻す犬も多いです。
この記事では、抜歯が必要になるケースや手術の流れ、退院後のケア、そして抜歯を防ぐための予防法までを詳しく解説します。
ぜひ最後までお読みいただき、愛犬が万が一抜歯が必要になったときに参考にしていただけると幸いです。
抜歯が必要になるのはどんなとき?
歯周病は初期の「歯肉炎」の段階であればケアや治療で改善できることもあります。
しかし、歯周病が進むと、歯を支える骨(歯槽骨)が炎症により溶けるように壊れていき、歯がぐらつくようになります。
歯のぐらつきは「歯周病がかなり進行しているサイン」であり、この段階になると抜歯が必要になることも多いです。
他にも、
- 歯肉から膿が出ている
- 強い口臭がしている
- 痛みで食べにくそうにしている
といった症状がある場合も、無理に歯を残すと痛みや感染が続き、犬に大きな負担がかかります。
そこで、健康な歯や生活の質を守るために抜歯が必要になります。
歯周病の進行度合いと抜歯の目安
歯周病の進行度と症状、必要な処置、抜歯の目安を表にまとめました。
| 進行度 | 主な症状 | 必要な処置 | 抜歯 |
| 健康 | ・歯茎はピンク色で引き締まっている ・口臭なし | ・毎日の歯磨き ・定期検診(半年〜年1回) | 不要 |
| 歯肉炎(初期) | ・歯茎の赤み、腫れ ・出血することがある ・軽い口臭 | ・歯磨き強化・スケーリング | 不要 |
| 軽度〜中等度の歯周病 | ・歯茎が下がり、歯が長く見える ・歯がぐらつく ・口臭が強くなる | ・スケーリング | 場合によっては抜歯 |
| 重度の歯周病(末期) | ・歯が大きく揺れる ・歯茎から膿や血が出る ・食べられず体重減少 | ・全身麻酔下での抜歯 ・抗生剤や鎮痛薬の投与 | ほとんどの歯が抜歯対象 |
スケーリングは、超音波スケーラーで固くこびりついた歯石を落とす治療で、全身麻酔下で行われます。
同時に、歯と歯茎の間にできた隙間(歯周ポケット)の中の歯石や細菌を徹底的に洗浄します。
これらの治療は歯周病の進行を止める効果がありますが、歯槽骨が大きく壊れている場合は抜歯が必要です。
全部の歯を抜かないといけないことはある?
以下のようなケースでは、犬の健康と快適さを優先して全部の歯を抜く「全顎抜歯」を選択することもあります。
- 歯周病の末期で、ほとんどの歯がぐらついている
- 歯槽骨が大きく破壊されている
- 膿や炎症が口全体に広がっている
- 痛みが強く、食事に苦労している
無理に残すより抜いてしまったほうが、犬にとって幸せなケースもあります。
また、口臭がなくなり、よだれや膿も減るため、飼い主様との生活も快適になることが期待されます。
不安な点は獣医師にご質問いただいたうえで、治療をご検討ください。
ご飯は食べられるの?
犬は、歯がなくても舌と歯茎を使って丸呑みしたり、すりつぶしたりして、フードを食べることができます。
処置を行うことで歯のぐらつきや炎症による痛みから解放され、むしろ食欲が戻る犬が多いです。
犬の抜歯手術の方法

犬の抜歯は、全身麻酔下で手術を行います。
ぐらついている歯を抜くだけの処置なら、1本につき数分で終わることが多いです。
奥歯は根がしっかりしているため、歯肉や歯槽骨を切り、歯を分割して取り出した後に縫合します。
工程が多く、1本につき30分程度かかることもあります。
手術中は麻酔で眠っているため、犬が痛みを感じることはほとんどありません。
抜歯後は鎮痛薬や抗生剤を使って、痛みや感染をコントロールします。
ほとんどが日帰りでの処置
歯以外は健康な犬なら、麻酔から覚めれば自宅に帰れます。
シニア犬や心臓、腎臓などに基礎疾患がある犬は1泊入院し、経過を観察することもあります。
退院後のケア
抜歯後のケアについて、飼い主様にお願いしたいポイントをまとめました。
- 通院:数日~1週間後に経過観察のため来院してください。
- 薬:鎮痛剤や抗生剤は指示通りに服用させましょう。
- 食事:術後はウェットフードやふやかしたフードにして、歯茎に負担をかけないようにしましょう。
- 歯磨き:抜歯部位が回復するまでは控え、治ったら徐々に歯磨きを再開してください。
上記の内容は、状況に応じて獣医師から説明させていただきます。
心配なことがあったら、お気軽にお問い合わせください。
抜歯にならないためにできること
歯周病の進行を防ぐために一番重要なことは、毎日の歯磨きです。
犬用の歯ブラシやガーゼを使って歯垢をしっかり落としましょう。
歯磨きが苦手な場合には、デンタルガムやデンタルケア用フード、歯磨きジェルなどを上手に取り入れてみましょう。
さらに、歯石や歯槽骨の状態を確認するためにも、半年〜1年に1回のペースで動物病院でチェックを受けることをおすすめします。
まとめ

犬の歯周病は、歯のぐらつきがみられるくらいまで進行すると全身麻酔下での抜歯が必要になります。
多くは日帰りで退院できますが、その後は定期的な通院と飼い主様による自宅でのケアが必要になります。
大切なのは、抜歯にならないように予防すること。
毎日の歯磨きやデンタルケア、定期的な動物病院でのチェックで、愛犬の健康な歯を守ってあげましょう。
京都府山科区左京区の動物病院
みささぎ動物病院